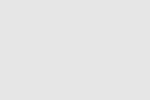述べるべきことが4項目以上あるなら、まず「分類」せよ
言いたいことがたくさんあるからといってそれらをやみくもに述べ立ててはいけません。項目数は絞り込むこと。そして、これ以上絞り込めないとなったときには、 以下に述べる二つの工夫が重要になってきます。
- スポンサードリンク -
どうしても細かくややこしい話をしなければならないときがある
複雑なもの・内容が盛り沢山なものを分かりやすく説明するのは難しいことです。
そういうとき、まず考えるべきことは枝葉を極力そぎ落として「幹」の部分で文章をまとめることです。
しかし、「枝葉」の部分の了解を取り付けることこそが説明の目的である場合、そのように済ませるわけには勿論いきません。 そういうときに相手に話を受け入れてもらい、理解を得るにはどうすればいいのでしょうか?
ラベルを付けて項目数を絞る
細かい話が重要・不可欠だからといって、それらを機関銃のように相手にぶつけるなどというのは大愚策です。
『エンジニアを説明上手にする本 相手に応じた技術情報や知識の伝え方』(開米瑞浩著)は、 こういう場合には次のことを試みよと提案しています。
- いうべきことを4項目以内にまとめる。
- 分類された項目それぞれに「内容を大まかに表す」ラベルを付ける。
項目数
人間が一度に頭に入れて置ける情報には限りがあります。項目数を少なく絞ることは、読者を置き去りにしないために大切な工夫です。 ちなみに『論理が伝わる世界標準の「書く技術」』(倉島保美著)では「3項目に分類せよ」と提言されています(過去記事参照)。
どうしても言いたいことが多数ある場合でも、視点を適切に保てば、少数項目に分類する可能性は必ず見えてきます。大項目に分類したのち、 それぞれの項目の中をさらに3-4項目に分類し、入れ子状・樹状の分類構造を作ることを考えてみましょう。
ラベルをつける
分類によって生まれた項目のそれぞれに、内容を要約する単語またはフレーズをラベルとして付加します。開米氏はラベルを「単純ラベル」と「分類ラベル」の2種類に分類しています。 彼の定義によれば、単純ラベルとは文中に出てくるキーワードを抽出したもので、直接的に内容を要約したもの。これに対して、分類ラベルは文の内容を抽象化したものです。 「考察」とか「提言」とか「目標」とかが「分類ラベル」の典型例といえます。単純ラベルよりは抽象的で包括的です。
この「分類ラベル」には次のような効能があるといいます。
- 説明すべきことが文章から抜けていないかチェックが容易にできる。逆に無駄な重複もあぶりだせる。
- 「違う場面で応用できる共通のパターン」を抽出することによって、過去の経験を応用しやすくする。 これにより、専門知識を共有していない人同士での相互理解が容易になる。
「分類ラベル」の活用により、趣旨を追いやすく理解しやすい文章が最終的に出来上がるというわけです。
まとめ
- 言いたいことがたくさんあるなら、分類して項目数を減らせ。
- ラベルで内容を要約せよ。
Tweet
![]()
執筆xyz公式ツイッターアカウント@tsuzurikataにてコメント/フォロー受け付けています。
- スポンサードリンク -